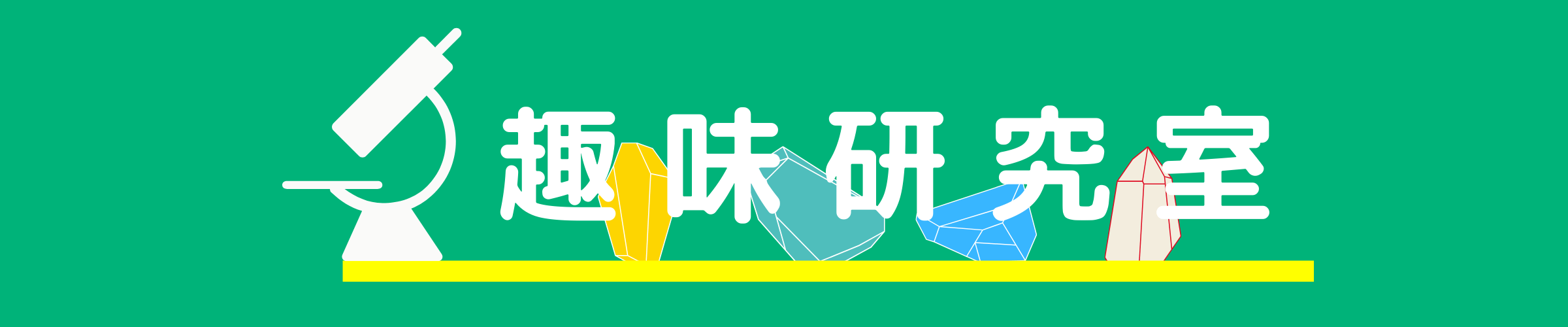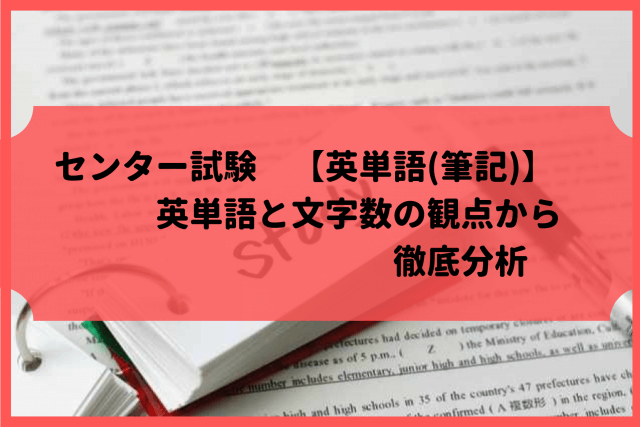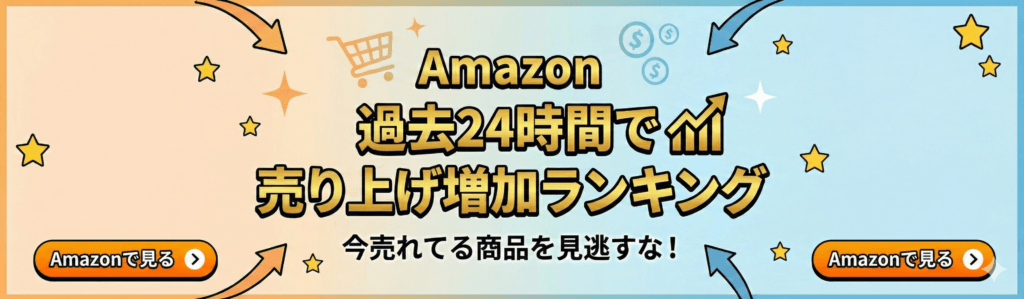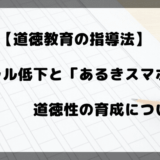(※本ページ内のリンクには広告が含まれています。)
多様な視点からセンター試験の分析が行われていますが、今回は平成30年度(2018年)のセンター試験、【英語】筆記試験の単語数と文字数の観点から各問を分析します。
ちなみに、英語のセンター試験で出題される英単語は、中学英単語1200語+高校英単語1800=計3000語となっています。
独立行政法人大学入試センター、Toshin.com、大学受験パスナビなどでセンターの過去問を見ることができます。
各問の単語数と文字数一覧
| 単語数 | 文字数 | |
| 問1 | 28 | 202 |
| 問1(A) | 12 | 73 |
| 問1(B) | 16 | 129 |
| 問2 | 520 | 2362 |
| 問2(A) | 215 | 1005 |
| 問2(B) | 99 | 430 |
| 問2(C) | 206 | 927 |
| 問3 | 1135 | 5437 |
| 問3(A) | 438 | 2125 |
| 問3(B) | 697 | 3312 |
| 問4 | 1016 | 5265 |
| 問4(A) | 583 | 3242 |
| 問4(B) | 433 | 2023 |
| 問5 | 843 | 3875 |
| 問6 | 849 | 4188 |
| 合計 | 4391 | 21323 |
※英語で表記されている英単語、文字数、数字をすべてカウントしています。
問1(A)(B)
問題
問1(A)は、 次の問い(問1~3)において,下線部の発音がほかの三つと異なるものを,それぞれ下の①~④のうちから一つずつ選べ、(B)は次の問い(問1~4)において,第一アクセント(第一強勢)の位置がほかの三つと異なるものを,それぞれ下の①~④のうちから一つずつ選べと発音に関する問題です。
分析
文章を読むわけではないので、出題される問の中でもっとも少ない単語数28単語と文字数202字が使われています。
速読力を求められているわけではないので、単語数、文字数は少なめです。
問2(A)(B)(C)
問題
問2は(A)次の問い(問1~10)の 8 ~ 17 に入れるのに最も適当なものを,それぞれ下の①~④のうちから一つずつ選べ。ただし, 15 ~ 17 については,(A)と(B)に入れるのに最も適当な組合せを選べ、Bは(B)次の問い(問1~3)において,それぞれ下の①~⑥の語句を並べかえて空所を補い,最も適当な文を完成させよ。解答は 18 ~ 23 に入れるものの番号のみを答えよ、(C)は、次の問い(問1~3)の会話が最も適切なやりとりとなるように 24 ~26 を埋めるには,(A)と(B)をどのように組み合わせればよいか,それぞれ下の1~8のうちから一つずつ選べ、と文法と構文に関する問題です。
分析
問2から文章が出題されますが、(A)(B)は1~2文の文章で英単語314語、文字数1435字が使われ、(C)は会話文ですが1文が短めで単語数206語、文字数927字が使われています。
選択肢の単語や文章も短めで、問題を見直すのに時間を必要としません。
問3(A)(B)
問題
問3は、(A)次の問い(問1~3)のパラグラフ(段落)には,まとまりをよくするために取り除いた方がよい文が一つある。取り除く文として最も適当なものを,それぞれ下線部①~④のうちから一つずつ選べ、Bは次の会話は,ある大学で映像制作の課題について学生たちが話し合いをしている場面の一部である。 30 ~ 32 に入れるのに最も適当なものを,それぞれ下の①~④のうちから一つずつ選べと、読解力と速読力が求められる問題です。
分析
問3から文章が長くなりますが問5や問6に比べると短いです。しかし、問3がもっとも多くの単語数と文字数が使われています。以下の表を見てください。
| 単語数 | 文字数 | |
| 問3 | 1135 | 5437 |
| 問5 | 843 | 3875 |
| 問6 | 849 | 4188 |
英単語1135語、文字数5437字となっいます。
問3は問5や問6より文章は短いのですが、文章の数が多いのです。
よく問5と問6で速読力が求められると言われてますが、単語数から見ると問3がもっとも速読力が求められます。
問5や問6は1つの文章を読めば複数の問題を解答することができるのに対して、問3は一問一答なので最後まで速く読んでしまいましょう。
問4(A)(B)
問題
問4は、A 次の文章はある説明文の一部である。この文章とグラフを読み,下の問い(問1~4)の 33 ~ 36 に入れるのに最も適当なものを,それぞれ下の①~④のうちから一つずつ選べ、次のページの料理教室に関する広告を読み,次の問い(問1~4)の 37 ~40 に入れるのに最も適当なものを,それぞれ下の①~④のうちから一つずつ選ぶ、速読力、読解力、図や表を読み取る力が求められます。
分析
問4は英単語1014語、文字数5256と問3に次ぐ英単語数、文字数です。(A)は長文ですが、(B)は表にも英単語が多く使われているために読む文章量は少ないです。
問5、問6よりも問4は選択肢の一文が長いのも特徴です。
問5、問6
問題
問5は、次の日誌の抜粋を読み,下の問い(問1~5)の 41 ~ 45 に入れるのに最も適当なものを,それぞれ下の①~④のうちから一つずつ選べ、問6(A)は、次の問い(問1~5)の 46 ~ 50 に入れるのに最も適当なものを,それぞれ下の①~④のうちから一つずつ選べ、(B)は、次の表は,本文のパラグラフ(段落)の構成と内容をまとめたものである。51 ~ 54 に入れるのに最も適当なものを,下の①~④のうちから一つずつ選び,表を完成させよ。 ただし,同じものを繰り返し選んではいけないと、速読力と読解力が求められます。
分析
問5は、英単語843語、文字数3875文字、問6は、英単語数849語、文字数4188字が使われています。日東駒専・大東亜帝国の統一試験や一般入試より文章は長く、英単語数と文字数が多いためある程度のスピードで読むことが求められます。
単語数から各問の時間配分を考える
最後に、単語数から各問の時間配分について考えます。
平成30年度(2018年)のセンター試験、【英語】筆記試験で使用されている総単語数は4391語で、試験時間は90分です。
単純計算すると、
4391語÷90分=約49語/1分間
で1分間に約49語を読むことが求められます。
| 単語数 | 時間(分) | |
| 問1 | 28語 | 30秒 |
| 問2 | 520語 | 11分 |
| 問3 | 1135語 | 23分 |
| 問4 | 1016語 | 21分 |
| 問5 | 843語 | 17分 |
| 問6 | 849語 | 17分 |
| 合計 | 4391語 | 89分30秒 |
問1を30秒で解くことはできませんし、問題を見返す時間を含まれていませんから、実際はもっと各問を速く読まなければいけません。
しかし、時間配分の目安にはなるかと思いますので参考にしてみてください。